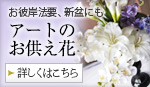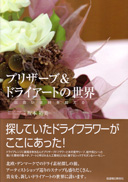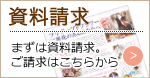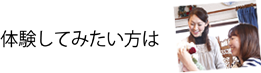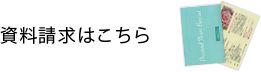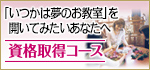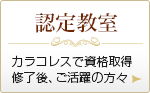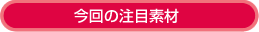

このふわふわユニークな素材に一目ぼれの方が多いのでは?
ドライアートの世界ではフィンランドモスまたはアイスランドモスと呼ばれます。
ドライアートになじみのない方には、ミニチュア模型の樹木に使われているスポンジみたいな植物。思い出していただけました?
そして、フィンランドモスの最大の存在価値が、あのトナカイたちの主食!であることです。トナカイゴケ、ハナゴケなどとも呼ばれる地衣植物です。はじめてそれを聞いたときには信じられませんでした。だってどんなにたくさん食べてもおなかにたまりそうにないのですもの。何十キロもの荷物を引いたりできるのかしらって・・・。

でも北極圏の林の地面を、このフィンランドモスが一面覆っているのだそうです。
モスとは呼んではいますが、地衣植物はコケではありません。菌類と藻類の共生体なんですって。ちょっと難しいですね。
コケのなかまは葉緑体をふくんだ細胞で、葉とくきの区別がありますが、地衣類というのは葉、くきの区別がなくて乾燥や極寒といったよりきびしい環境にも適応するみたいです。
そうそうフィンランドモスからはなれちゃいますが、あの理科の実験でおなじみのリトマス試験紙も、リトマスゴケと言う地衣植物の成分から出来ているのですって。まだまだ不思議の多い地衣植物です。

フィンランドモスとアジサイのグリーンの対比を見事に表現した、 小林康子さん(本部BASICコース)の作品
ドライアートをやっていて楽しいのは、本当に自然って様々だなあって思うとき。
同じ種類の植物でも、環境に合わせてどんどんかわってゆくたくましさを感じたときかな。
「どうしたらこんな形の木の実が出来るの?」とか「いったいあなたはどんな理由でそんなに素敵なの?」って・・・。
わたしが形作るんじゃなくて、「もうすでにそこにあるエネルギー」を大切にしたいと、いつも思っています。
さあそのフィンランドモスですが、地面をおおうクッション材に使うことが多いです。
ワイヤーでつくったUピンで優しく止めて、その柔らかさを引き立ててあげましょう。
静かに切り込みを入れてあげると、丸いかたまりが段々平らに広がってゆきます。
大きな面を覆うときは上手に広げて使いましょう。

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)