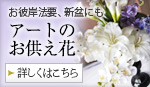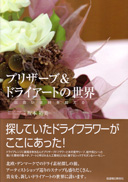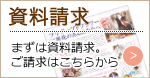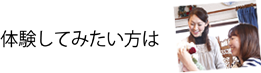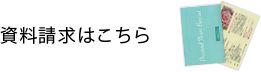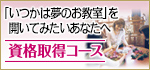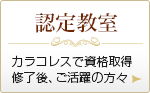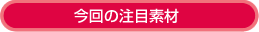

狭い部分のアレンジに大活躍する葉物です。ヒカゲノカズラは長い蔓の先にスギの葉のような枝を付けます。
同じ仲間でもう一方のタチカズラは、形はほぼ同じですが、長い茎の部分は地中にあります。
そうそうお寿司屋さんのケースの中を飾る、杉みたいな葉です。
ヒカゲノカズラの学名はLycopodium clavatum。マンネンスギとも呼ばれるタチカズラの学名はLycopodium obscurum。
彼らの見た目はスギに似ていますが、スギは裸子植物、一方ヒカゲノカズラたちはシダ植物なのだそうです。
涼しげなシダ植物ですが、かつて彼らが大繁栄した時代があります。古生代石炭紀、今から3億年も前のこと。
現代のヒカゲノカズラたちの「小葉」の部分はせいぜい数十センチ。ところが当時はなんと樹高30メートルにも及んだとか。それらの大森林が炭化したものが、現在の石炭や石油になっているのです。とてつもなく長?い歴史を持った素材なのですね。

プリザーブド加工のタチカズラ
また、ヒカゲノカズラやタチカズラの胞子を集めた粉末は、「石松子(せきしょうし)」又は「リコポジューム(こちらは学名そのものですね)」と呼ばれ、意外な場所で役立っています。湿気を吸収しない性質を利用し、皮膚の湿疹をおさえる生薬として使われたり、線香花火の発火剤などにも使われてきたそうです。
ほかには果物などの「花粉増量剤」。う?ん、これはなじみが薄いですが、人工授粉する時花粉100%だと発芽率が落ちるそうです。それをカバーするためにこのヒカゲノカズラの胞子を増量するのですって。
あと、面白いところでは「指紋の検出」に使われているそうです。
なんと、ドラマでおまわりさんがパタパタやっていたあのお粉は、ヒカゲノカズラの胞子だったのね!
地球上に登場の歴史が長いだけに、まだまだ、文学そのほかにもたくさん顔を出しているヒカゲノカズラたちです。
そんな歴史に想いをはせてアレンジするのも楽しいですね。

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)