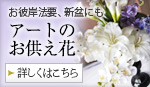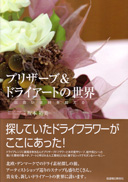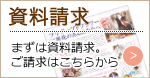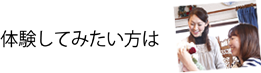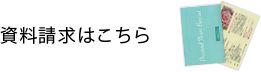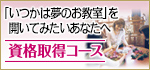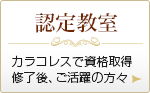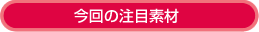

高級家具の材料として名前を聞いたことがある方も多いはず。「マホガニー製の・・・」という。中南米原産で20~30mになるセンダン科の高木です。
硬くて加工が施しやすくまた独特の美しい光沢もあることから、ギターのボディにも使われます。

マホガニーの実は熟すとばらばらになってしまうことから、中心部の果実とまわりを囲むカラのような部分が別々に流通しています。
写真の実はオレンジ色に着色されたものです。
実のほうも幹に劣らず硬くてワイヤリングするのが大変。「この親にしてこの子あり」といった感じです。
世界に3種類ほどあるマホガニーですが、乱伐が進み現在では商取引がワシントン条約で制限されています。
ところでワシントン条約は野生生物を守る法律ですが、絶滅危惧の度合いによって1から3段階まで規制が分かれているのをご存知ですか?
特に1は希少性が高いと言う事で国際間の取引はもちろん、「種の保存法」によって日本国内の取引も禁止されています。
1にはウミガメやゾウやオランウータン・・・べっ甲などの加工品も含まれます。

気になるマホガニーですが、国際間は制限されますが日本国内での流通は自由とのことです。すでに輸入されているものは規制の対象にはならないと言う事ですね。(経済産業省調べ)
世界各地で植栽もされ始めているようですが、いずれにしても希少性が高い植物で、もしかしたら天然の実をアレンジに使えるのもあとすこしかもしれません。
また本物のマホガニーが入手しづらくなった最近は「フィリピン・マホガニー」の名で流通している材木があります。これはセンダン科とは別種のフタバガキ科のラワン材。ベニヤ板の材料ですね。このフタバガキの実がまた羽子板の羽みたいでユニーク。またいつかここでご紹介したいと思います。
ドライアートは世界の植物につながっているので、興味の入り口もたくさんですね。

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)