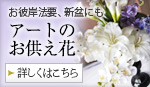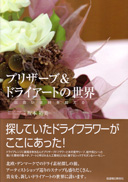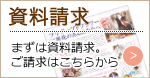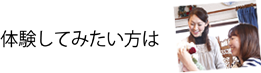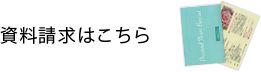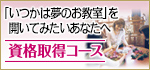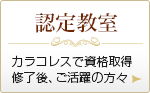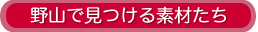

イガイガの実は、マツボックリとはまた一味違う風合いがあります。
ヤシャブシは漢字で「夜叉五倍子」と書きます。不思議な文字ですね。
夜叉は古代インドの神話に登場する鬼神(yaksa)が、仏教として伝来して日本では善い神様に変身したのだそうです。

確かにこの実の規則正しいイガイガは善人にも悪人にも取れる不思議な魅力があります。「規則性」というのは心を癒してくれるので、私にとっては善い神様かな・・・。カバノキ科のヤシャブシの果穂は、シラカバに似て長く垂れ下がりますので、この風情から「夜叉」の名がついたとも言われます。
さて夜叉に続く次の「五倍子」、これはフシと読んで、虫こぶのことです。虫こぶって見たことありますか?木の葉や幹に昆虫が卵を産んで、組織を異常増殖させてこぶ状にしてしまうことです。タマバエなどは悪名高いですが、そのほかにも有効利用されてきたものには白髪染めやお歯黒の材料になるような虫こぶがありました。ヤシャブシの果実もタンニンを多量に含んで染色に使われたことから、「フシ」という名がつけられたそうです。
そうそう「虫こぶ」といえば、猫にマタタビのあの「マタタビ酒」に入れるのも、実はマタタビの本当の果実ではなくて、マタタビミタマバエがつくった「虫こぶ」なんだとか・・・。知りませんでした。
ヤシャブシは比較的野山のどこでも見ることができ・・・というよりは、放っておけばどこにでも入り込んじゃう元気のよい樹種なのだそうです。パイオニアなんですね。それからこの樹木も白樺と同じ「口腔アレルギー」を引き起こす原因となるそうで、場所によっては伐採も進められているそうです。
ただしもちろん悪いことばかりではありません。ヤシャブシの根には根粒といって細菌との共生によってこぶができています。この根粒菌が地面の中でたりなくなりがちな窒素を集めてヤシャブシに提供していますので、葉の窒素濃度が高くなって落ち葉により土壌も肥沃になります。荒れた土地を緑化するためにも使われてきたのだそうです。
リースの素材としてもおなじみのヤシャブシの実ですが、作品つくりとともにこんなエピソードたちも思い出してくださいね。

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)