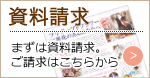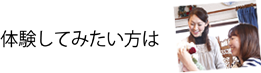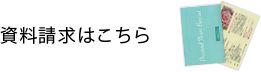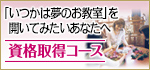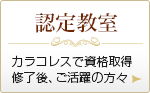学生時代にたった1ヶ月でやめてしまった洋菓子店のアルバイトがある。
東京のベッドタウン、にぎやかな駅前商店街のちょうど最初の角にあるのがそのお店だった。半分が小さな喫茶店、もう半分が洋菓子店、また隣接した敷地には不動産会社もあるこじんまりした地元資本の多角経営だった。
50代の働き盛りの主婦ふたりが常勤のスタッフで、新米の私に丁ねいに仕事の手順を教えてくれた。ちいさなお店なので、洋菓子店が暇なときは隣の喫茶店のお手伝い。そこにはいつものどかにパイプをくわえたマスターがいて(彼がこれらのお店のオーナーなのだが)、おいしいココアの入れ方などを伝授してくれたりもした。
結構楽しくて気に入っていたのだ、ああいうことさえ気にとめなければ・・・。
ある日、洋菓子店のレジを担当していた私は、反対側のショーケースの前で30代の女性客がカステラを選んでいるところを目にした。その女性は入念に長細い箱をひっくり返して製造年月日(当時は賞味期限ではなかった)を確認していた。
「これください。」「はい、ありがとうございます。」
そう言って商品を受け取った私は振り向いて、包装用のテーブルで紙袋に入れ始めた。
ところが横にいた先輩の1人が、私がそのカステラを包むのを制止して、同じ種類のカステラの包みをテーブルの下から取り出しあっという間に差し替えた。
女性客と私たちの間にはレジに続く背の高いガラスのケーキケースが置かれていて、死角になっているのだ。
「ありがとうございました。」にこやかに見送る彼女に、一呼吸置いて何がいけなかったのかたずねた。
テーブルの下を見て一目瞭然。売れ残ったカステラがいくつも積まれていたのだ。
「このカステラをお客さんが選んだときには、それとなくこちらの古い方と差し替えするように言われているの。」
「でもさっきの人、日付しっかり確認していましたよ。」と言うと、「大丈夫、家に帰ってまで確認する人いないから。」
それから、そのカステラをお客さんが選ぶたびレジで古いものと取り替えて・・・。
こういうものなんだろうかと思いながらも、何だかすごく申し訳ない気がしていた。カステラ買わないでくれるといいなと。
ある日良いアイディアを思いついた私は店員仲間の一人に進言した。「この隠してるのを全部お店に出しちゃったらどうでしょう。全部売れるまで新しいのを問屋さんから買うの辞めて。そうすれば一気にきれいになるしお客さんにウソつかなくてもいいですよね。」こんなにストレートに言えたかどうか怪しいが、とにかくそのような主旨を伝えた。
が、結局その提案は陽の目を見ることにならなかった。
1ヶ月がたち、はじめてのお給料日がきた。
オーナーの奥様が現金で給料を渡してくれ、同時に「人手が足りたから来月から来なくていい」旨を言い渡された。
また他を探せばいいやと気楽に思いながら、逆にカステラの件から開放されたのは少しうれしかった。
数日後、学校の帰り道それとなくお店をのぞくと、私と同じくらいの年代の新人アルバイトが働いていた。彼女は「あの作業」をどう思うだろうかとちょっと気になった。
幸い私は1ヶ月でくびになってしまったのでそのあとお客さんを裏切る事はなかったが、もしそこで勤めが続いていたらどうなったのだろう。
日常にまぎれて「あの作業」にも慣れてしまったのだろうか・・・。
カラコレス・プリザーブド&ドライアートスクール代表 坂本裕美

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)