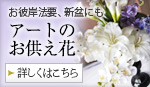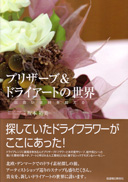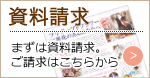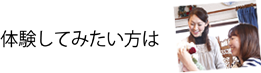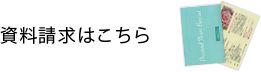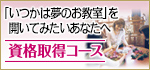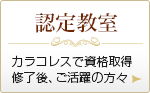ある日、日の当たる窓辺で面白い光景に出会った。上下さかさまに置いたヒマラヤスギの松かさの、裏側が開いてタネを落とそうとしていたのだ。
ふつうなら表側のバラの花のような形をした松かさが、大きく開花する風に一枚ずつはがれ、中の翼つきのタネがまかれるのだが。
表がダメなら裏側を開いてなんとしてもタネを外へ・・・「種の保存」への執念を感じた一瞬。
ドライアートを仕事にしていると、植物の不思議に常に遭遇する。
私達が小手先で何かを作り出すより前に、素材そのもののエネルギーに圧倒されてしまうのだ。
「乾燥した」植物のなかにエネルギー?と思われるかもしれないが、二千年たって芽を出した蓮のことを思い出してほしい。
発芽するのに良い条件になるまで休眠するのは、野生の特性のひとつではあるけれど、いったいなんという生命力!
彼らは芽を出す機会を、気が遠くなるほど長~い間待っていたのだから。
通常100種類以上のレッスンが同時進行で行なわれている私のスクールでは、用意する素材は700から多いときで1000種。あつかう素材のバリエーションがものすごく広い。
中でもユニークなかたちの木の実はいつもアレンジの人気者だ。
ただ、私達がいう木の実とは、じつは種子(seed)ではなく、さや(pod)の場合もおおい。これは野生と穀物のタネのつくりのちがいからくる。
野生のタネはさやからかんたんに離れるつくりになっている。目的は「種の保存」だから、実ったら一刻も早く自立しなければならないのだ。それぞれが自分の重さで落下したり、羽や翼がタネについていて遠くへ飛ぶ事が出来たり、色々工夫してさやから離れようとする。
一方穀物の方は、いっせいに実り収穫してもらわなければいけないので、どこかへ勝手に飛んでいってはこまる。じっとさやに付いたままでいて、おとなしく収穫されるのを待っていてくれないと。
ドライアートに入れる木の実は、世界中の野生種を集めたもので、すでにそこに種子がないことも多く、さやの活躍の場が広い。
本当にいろいろな形のものがあると感心。
さやなのに、遠目には花のように見えるものや、ハート型、星型、トリュフみたいなの・・・。
マツやスギといった裸子植物の松かさは、種類によって大きさや形も様々。他の国には「これが上から落ちてきたらケガするだろうな」と思うほど大きなマツボックリもある。
そしてどれもが完璧に美しくデザインされている。
話題のプリザーブドフラワーのウェディングブーケを10年以上前から提案してきた。
華やかなプリザーブドフラワーだけでは、単調で「これ見よがし」なブーケになってしまう。
けれど幸いなことに、カラコレスの場合は影で支えているこうしたたくさんの副素材たちがある。
自然のエネルギーをおすそ分けしてもらっているような気がする。
カラコレス・プリザーブド&ドライアートスクール代表 坂本裕美

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)