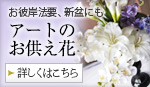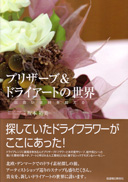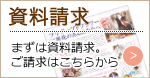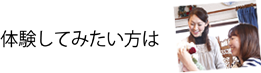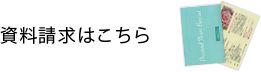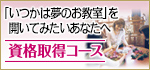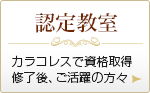中学2年生の長女あてに来た学習教材のダイレクトメール。
いつもなら封を切らずにゴミ箱へ直行なのだが、この日は、長女が中に入っていた漫画のPR誌だけを抜いたようで開封してあった。
ふと中の一枚を手に取ると、作文の添削講座が始まります、という内容。
中学2年生ってどんな文章を書くのだろうと、つい興味をもった。
というのも、超マイペースなわが娘の書く文章は「青い空と白い雲、のんびりした時間が好き~~」というような現実離れなのが多い。
それはそれで、まあいいかと思ってはいるが。
ビフォー、アフターとあり、実例が添削後どう変わるかが分かるように、並んで記載されている。
どうも提示された資料文を読み解き、自分なりの考えをまとめよというような課題らしい。
永遠の命に絡めて、自分の時間の使い方に思いをはせたその文章に、「ふ~ん、中学2年生ってこんなしっかりした文章書くんだぁ。」なんて感じながら両者を見比べて「・・・?」。
添削を受けずに書いた最初の文章の方が、生き生きしているのだ。
直した方は、それなりにまとまっているが、エネルギーが感じられないし「想い」が伝わってこない。平らになっちゃった、といったらよいか・・・。
私の主観によるところが大きいだろうな、とも思い、最初の文章の添削のポイントを見ると、「設問要求・条件を満たしている」と、「文章の流れ、構成を意識している」がそれぞれBランクの評価になっていた。
やっぱり最初の文章は設問の答えになっていないという事みたい。
「答えになっていないけど、こっちの方がいいじゃない」なんていう私のような試験官がいたら評価がめちゃめちゃになってしまうのだろうな。
とは思うものの、これが試験でなくても同様の事をたびたび感じている。
「直されてしまったがゆえの、勢いのなさ、傾きのなさ、つまらなさ・・・」。
レッスンをしていて、「ここを直すと、誰もが納得するまとまりのあるデザインになる」というときでも、私たちはあえて直さないことがある。
「その人らしさ」が作品ににじみ出ているとき、そちらを大切にしたいと思うから。それは言い換えればバランスの悪さにも通じる。
見本を中央に、一糸乱れぬ同じ作品が並ぶレッスンを、どうしてもする気になれないのは、そこに勢いやエネルギーが感じられないから。
「いきおい」とは、バランスの崩れたところにしか生じないと思っている。
カラコレス・プリザーブド&ドライアートスクール代表 坂本裕美

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)