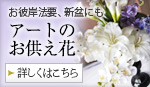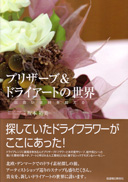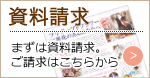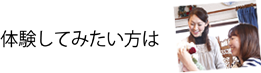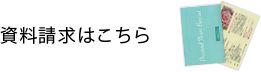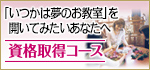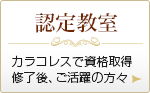対比するもの

玄関脇の二階まで届くもっこうバラが、今年も満開の季節を迎えました。
グリーンの葉にふち取られた一面の黄色い小花が、この数週間、眼を楽しませてくれるはずです。
さて風薫る五月の一日を、上野の国立西洋美術館で開催された、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの展覧会に出かけました。
日本ではじめての、そしておそらくこれが最後であろうと言われているラ・トゥールの展覧会です。
17世紀、フランス東部ロレーヌ公国で活躍した画家ですが、30年戦争など戦乱にまみれ、現在残る真作は40点余りにすぎません。
宗教画が多いようですが、作品解説はプロの美術家におまかせしましょう。
宗教画とは別の視点しか持ち合わせていない私にとって、ラ・トゥールといえば「光と闇の対比」。
とくに、ろうそく一本の光の効果を使い人物を映し出す作風から生まれる「静けさ」は、今回集められたたった20点ほどの真作でも充分伝わってきました。
ラ・トゥールの作品に出会ったのは、今回が初めてではありません。
15年ほど前、クリスマス直前のパリ、夫と出かけたルーブル美術館の閉館間近、人気のない展示室で、ラ・トゥールの作品「灯火の前のマグダラのマリア」と対面しました。

ろうそくの明かりに照らされ、ひざに頭蓋骨を置き頬杖をつくマグダラのマリア、この気品ある絵に会いたくて訪れたルーブルでした。
作品の「静けさ」とは対照的に、一歩外に出るとシャンゼリゼのクリスマスイルミネーションがまばゆいばかりだったのをおぼえています。
残念ながら、今回はルーブルの「マグダラのマリア」との再会はなりませんでしたが、ラ・トゥールの作品が「対比」という言葉を思い起こさせました。
対比…比べること。違ったものを対立させ、特性をはっきりさせること。
日常での些細なことも、対比の中で確認をしているわけですよね。
手のひらに収まるほどの、もっこうバラの黄色とグリーンの対比からはじまって、もっともっと…もっと大きな課題まで。
ありあまる対象から何を選び出して対比させるか…そんなところにその人の感性が現れているような気がしました。
カラコレス代表
坂本 裕美

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)