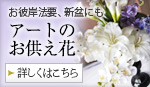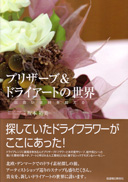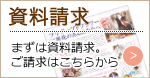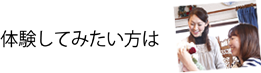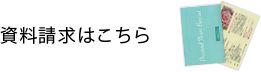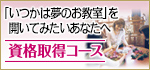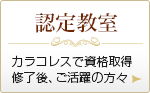【この記事は2014年のものです。】
50才を過ぎると、若いころ描いていた情景を
たいてい達成してしまっているのを感じます。
やってみたかったことを羅列して、
出来るところから一つ一つ、
足元を見て一歩一歩地味に進んでいると思ったら
振り返ったらほぼ思うような世界を実体験していたという感じ。
「何かを使って何かを作る。
それでその何かがほかのどこにもないような世界」。
「何か」ばかりではありますが(笑)、
今ではそこに複数の具体的な言葉を入れることができます。
なにしろ思い描いていたのが小さな世界ですから達成も早い。
この夏、つい先日まで困っていたのは、
小さな世界で達成感を得たので、
次に進む理由が見当たらないことでした。
このモチベーションのなさを跳ね返すのは、
プラスのエネルギーではないような気がして、
ではマイナスのエネルギー・・・。
リセットする。ゼロにする。解体する。捨てる。
死んだつもりになる。
で、エンディングノートを作り始めました。
市販の素敵なタイトルのついたものではなく、全くの私仕様。
カスタマイズされたものでしか満足できないので。
そこに記すのは幻想でもなく哲学でもなく
今と今後自分を取り巻く事実。
そこまで来てようやく、自分を取り巻く環境、つまり事実が
50才までとは変わってきていたのだとわかりました。
それを確認できて、ようやくモチベーションが戻ってきました。
「ベクトルの向かう先」を再構築した夏です。
【こちらは2014年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【この記事は2014年のものです。】
夫の地元の函館には「鯨汁」という郷土料理があり
俳句の冬の季語にもなっているそう。
塩鯨に根菜や山菜をたっぷり入れて、煮込み年末年始に供される。
昨年末、一人暮らしを始めた義父のもとに私達夫婦で帰函し、
料理上手だった義母には及びもしないが
この私が鯨汁はじめ、正月料理担当として腕を振るうことになった。
義母がいつも買っていたお魚屋さんは、
地元の人しか行かない本当に小さな小さなお店で
ご主人と奥さんが立ち働いているスペースは2人でいっぱい。
ショーケースも小さなものだが、その代り扱うものは
厳選された活きの良い魚や貝や干物ばかり。
珍しい魚もあって、
函館に帰るとこのお魚屋さんに来るのが楽しみだった。
「悪いね、この年末はもう予約しか扱わないんだよ」とご主人。
ああそうだった、いつも義母はお刺身を予約していたことを思い出す。
ダメもとで「鯨汁を作ってみたいんですけど」と聞くと
「塩鯨だったらひとつあるよ」と小さな白い塊を出してくれた。
湯通しの仕方や根菜や山菜の合わせるものも聞いて。
お正月に帰ることは少なくて、
いつもは暖かくなった5月の連休が多いので、
私もほとんど食べたことのない鯨汁。
でもこれがなかったら義父は元気にならない。
その他の材料を買いに地元のスーパーに立ち寄ると
やっぱりそこにも同じくらいのサイズの塩鯨を売っていたが、
価格は先ほどの6分の一。
あららこんなに違うの?とびっくりしたが、
そのとっておきの塩鯨で作った鯨汁はコラーゲンがたっぷり栄養たっぷりで
塩鯨の細切れも柔らかくてプルプルで解けてしまいそう。
懐かしそうに「おいしい」と義父。
後で聞いたら、質の悪い塩鯨は固くて噛みきれないのだとか。
良かった、初制作の料理が噛みきれないようなものではなくて。
そのお魚屋さん、私にとってはまるで「宝箱」のような存在。
「小さくて」「質の良い物を扱って」「今いるお客さまを大切にし」
「行けば必ず美味しい物がみつかる」という期待を外さないのもすごい。
それを後押ししているのが、
納得のいく品物が売切れたら店を閉める潔さ。
私の仕事もそのような方向に行くのではないかと思う。
「小さいままでいる」って大事なこと。
【こちらは2014年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
そんなことをやっている過程での、
漏れのあった記事をアップしてみました。
昨日の自分のようです。
あまり変わってないわねと(笑)。
家にいて、静かにできることをやってみています。
【この記事は2016年のものです】
作品制作の最中なのか、
完成間近の時なのか、
完成の瞬間なのか、
飾って素敵って思えた時なのか。
あるいは贈ってありがとうと喜んでもらえた時なのか。
どの瞬間もモノを作るひとにとって
比べがたい楽しい時です。
けれどそれとは別に、
全身の血が沸き立つような、
集中力と引き換えに感じるわくわくがあります。
それは、何かがはじまる前。
静かで、
すべては収まるところに収まっている。
きれいになった机の前に立ち、
これから何を選ぶかはわたし次第。
その瞬間の緊張感は特別です。
形になりだしたときというのは、
もうプランを実行しているにすぎません。
カラコレスを一つの世界と考えると、
どんな素材をそろえ、どんなカラーを打ち出し、
どんな人たちに何をご提案できるか、行きたい方向は。
その一つ一つが作品であり、
わくわくを通り過ぎてきた作品です。
無事第20回生徒作品展、研究生のグループ展が終わりました。
そしてまた次のわくわくに向けて
収めるものを収めている時が今です。
【こちらは2016年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事をアップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【2013年の記事を上げています】
私は一生かかってもこうは呼んでもらえません。
気が利かないから。
もう、とにかく憧れるのです(笑)、気が利く人に。
私にとって最大最高の「気が利く人」はこの夏他界した夫の母でした。
彼女は化粧品やお洋服のお店もしていたので、
いつもお客さまに「○○だと思ったから、○○用意しておきましたよ」と、
タイミングをはずさず過不足のないサポートをします。
お客さまは「ここに来ればすべてわかってくれて受け入れてくれる」
という安心感から、義母を自分のおしゃれのコンシェルジュとしていました。
事実いつも義母の買付は「○○さんのためにこれを」という、
目的の決まった買い方。
そのサポートは嫁である私にも及んでいて、
「あなた、また海外に行くんでしょ、
化粧品の小さいの送っておいたから使いなさいね。」と
こまめに世話を焼かれていたのでした。
また、先日仕事である会社の女性の新入社員にお世話になりました。
その二十歳そこそこの女性が実に気が利いて、
義母と同じ匂いがするのです。
「坂本さん、これあった方が良いと思いましたのでやっておきました」・・・が
ほんの一か月の間に何回もあって、その働きぶりに感嘆しました。
年齢じゃないのね~!
「気が利く人」に共通しているのは周りが見えていることと先が読めること。
周りが見えず先を読めない私はすこしでもその世界に近づきたくて、
こういう時義母ならどうするかなと思うのですが
一向にその距離は縮まらないのです。
もう一層のこと、気が利かなくて周りが見えなくて
先も読めない代わりに○○ができる!という方向を目指すしかないわ。
その○○に入るものを、これからの時間を使って探します。
【こちらは2013年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事をアップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【2012年の記事を上げています】
8月のお盆休みの後半を、夫の実家のある函館へ出かけました。
長女が大学生になり、長男が中学で部活を始めてから
なかなか家族4人の時間が持てなかったので、
久し振りの家族旅行です。
20年以上前に夫と歩いた同じ道を家族で散歩しました。
異国情緒ただよう函館の街を見下ろす坂道。
観光地になっている、教会がいくつもある通りに
ソフトクリーム屋さんがこちらも数軒、熾烈な競争をしていました。
どこもアルバイトのお姉さんがお店の外で呼び込みをしています。
そのうちの一軒、主のおじさんが
「うちのアイスは〇○牧場の牛乳で」と
おいしそうな呼び込みをしているお店に立ち寄りました。
用意された木陰の椅子に腰を下ろして頂く、
北海道の牧場のしぼりたて牛乳のソフトクリームは美味しくて元気が出ます。
ひと時休ませてもらって、さあもう少し歩こうかと。
家族で席を立ってすぐ目の前の通りに出ると、
先ほどの呼び込みをしているご主人と目が合いました。
次の瞬間ご主人から出た言葉は
「いらっしゃいませ~、○○牧場の牛乳を使ったアイスで~」。
視線は私達を通り越して、
向こうからやってくる観光客に向けられていました。
お店が見えなくなるまで歩いた時、
ふと「最後が『ありがとうございました』だったらよかったのに」とつぶやくと、
隣にいた夫が「俺もそう思った」と。
おいしいソフトクリームをたべて行動が完結しているはずなのに、
なまじ目が合ったばかりに
予定外の行動に気持ちが完結しませんでした。
お客様にお渡しするのは
形ある商品ばかりではないなあと痛感です。
お帰り際、にこやかに目を見てお話しすること、
「ありがとうございました。またお待ちしていますね」と
お声掛けすることは、
絶対にお渡し忘れてはいけない「形のない商品」なのだと心がけています。
それをしないと私達も気持ちが悪いということは、
お客様と私たちのあいだにしっかり気持ちの交流がある証で、
仕事をしていて一番安心する瞬間です。
【こちらは2012年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【この記事は2013年のものです。】
「カラコレス」という屋号を付けるとき、
もう一つの候補に挙げたのが「アラベスク」という言葉。
別に5文字にこだわったわけではなく、
オリエンタルな幾何学文様のパターンが好きだったから。
けれど「アラベスクは重すぎる!」という妹からの一喝で(笑)、
カラコレスは「カラコレス」として生まれ命名されたのでした。
20年近く前。
先日訪れた戸隠の庵には、日本古来からの鬼瓦のコレクションが並び、
しかも博物館ならガラス越しにしか見られないような貴重な瓦を
手で触れられる距離で直に拝見できる。
その中の一枚に、鬼瓦に比べたら平らで軒の見える部分に
きれいな唐草文様の入った瓦がある。
「奈良時代の瓦で楔形(くさびがた)唐草という紋が入っています」と
庵の主の和尚様兼カメラマンの先生が教えて下さった。
くさび形というところがそっくりそのままオリエント。
大小2本のラインが描く唐草文様はリズミカルで、
どうやってこの時代にこうも美しく繊細で隆起したラインが出せたのか。
私の心をわしづかみにしてしまったこの瓦。
だってオリエンタルな幾何学の連続文様、好きなんだもの♪
奈良時代に各地で建立された国分寺の軒平瓦にも
この楔形唐草の仲間、「均整唐草紋」がほとんど入っているのだとか。
屋号になりそこねた「アラベスク」も
唐草模様そのものを意味していたりして、
好きか嫌いかに理屈はない。
好きなものはいきなりドキドキする。
そして、この先、好きか嫌いかに理屈がないところを
掘り下げていくことになるんだろうな・・・
そんな予感を一枚の瓦との出会いで察知した。
おまけですが、「カラコレス」はスペイン語で「かたつむりたち」。
のんびりゆっくりマイペースで。
【こちらは2013年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【この記事は2015年のものです。】
カラコレスの生徒さんにはおなじみの
「ガーランド」という手法があります。
クローバーの白い花で首飾りをつくる要領で
最初に芯にする2.3本を集め、それを元に一本ずつ加えて編んでいく手法です。
これですと、ベースがいらないので、
どんな長さに作ることもできます。
2013年にパリでディスプレイしたサロン・デュ・ショコラの
バラ4,000輪もこの手法で編みました。
はじめての方は、バランスよく花材を配置することが難しいので、
最初にイメージに合う形に花材を置いてみましょう。
それを端から編み込んでいくと
イメージ通りの仕上がりになりますと説明します。
慣れると15センチサイズのリースなど、
数分で作れるようになります。
そもそも生花のお教室ではないので、
生花を扱っている緊張感に比べるとまったくゆったりしたものなのですが、
それでもオアシスに挿していくようなデザインでは
挿し直しが難しいので多少は緊張します。
で、ガーランドの何が良いかと言いますと、
ダメだったらいつでも戻って編み直しができるのです。
気に入らなかったらもう最初から。
実際には皆さん慎重なのでそうそう編みなおすことはありません。
でも「失敗入しても大丈夫、やってみましょう。
気に入らなかったら編みなおせるから。」とお伝えし、
それが生徒さんに安心感を与えているようなのは確か。
最初からなんでも上手になど出来ません。
二度三度と回を重ねるごとにうまくなるのは当然のことです。
会社勤めをしていたはるか昔、新入社員に対して
「失敗しても大丈夫、やり直せばよいから、さあやってみましょう」と
指導していたらしく、
「失敗しないでねと言われることが多い中、それがとても救いだった」
と退職してから聞きました。
今と言ってることが変わらないではないか(笑)。
逆に言えば、最初からうまくいくはずがないと思うので、
大事な場面は限りないシミュレーションを繰り返します。
臆病者で不器用な私にとって
「やり直しできる」ことは、最も大事なのです。
【こちらは2015年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【この記事は2015年のものです。】
以前習っていた筝曲のお師匠さんが、ある日座禅の道場に行き、
ご自分の迷いについて和尚様に問われたそう。
その時の和尚様の応えが
「お箏を一生懸命弾くことが供養になります」だったとか。
当時まだ20代の会社勤めの私にとって、
おけいこ中にお聞きしたこの言葉は、
その後の数々の迷いを吹き飛ばす力強い支えになりました。
それを一生懸命おこなうこと自体が供養なら、
だれに遠慮もいらないではないの。
だれかの役に立つからとか、自分のプライドにかけてとか、
そういった面倒な感情はいっさい排除しても、
好奇心と一生懸命さがあればいい。
そうしてこの仕事をはじめて20年。
いつも楽しくて一生懸命です(笑)。
課題が多い中で、優先順位が錯綜する中で
その言葉はシンプルだけれど揺るぎがたい指針にもなりました。
さらに気が付くと、このごろいろいろ楽になっているのです。
それは、最近そこにもう一つの指針が加わったから。
「やらなければならないことなんて何もない」
年を経て怠惰になったわけでもないでしょうが、
一生懸命やるのも良し、やらないのも良しと思えるようになりました。
場や時や出会いがもたらすものを、
以前より大切に思うようになったからかもしれません。
こういう風に解決されることもあるのですね。
課題そのものがなくなるという形で。
まだまだ発見ばかりの毎日です。
【こちらは2015年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】
【この記事は2015年のものです。】
100歳で亡くなった祖母が、桜の季節にはよく
「あと何回この桜を見られるかしらねー」と、
つぶやいていたのを思い出します。
あれが確か70代でしたから、祖母はそれからずいぶん長い間、
自覚的に桜を楽しむことが出来たのでした。
桜はほかの植物にないくらい強烈に春を意識させるので、
「ああまた一年がたったのね」と、
私もこの年になって初めて祖母の気持がわかるようになりました。
本物の桜には痛い思い出もあります。
子供のころ、庭の桜の花びらの吹き溜まりに手を入れて遊んでいたら、
いきなりチクン。
びっくりして手を上げるとミツバチが渾身の一刺しで
しがみついていたのでした。
ハチも驚いたのでしょう。
ドライフラワーをメインに据えてレッスンしていたころは、
桜は素材としては縁のないものでした。
花びらが薄くて散ってしまう素材はドライになりませんから。
ところがアーティフィシャルフラワーを積極的に取り入れるようになって、
桜の花びらの一枚一枚がこうも繊細に表現されるようになったのかと
感嘆することしきりです。
ソメイヨシノや八重桜にしだれ桜に、色も鮮やかな山桜...。
昨年のあるイベントではエントランスの大きなポットを
アートの桜でいっぱいに活けました。
本物に見まごうほどの桜は、会場を一気に華やかに彩ります。
ドライフラワーでもなくプリザーブドフラワーでもない、
造花だからこそ表現できる「はかなさ」もあるのだと。
散る桜と散らない桜、どちらが好きか・・・
なんて野暮な発想は脇に置いておいて。
一瞬を本物で楽しみ、よりデフォルメされた世界を
作ったもので楽しみたいという、
欲張りなシーズンがもうすぐです。
【上記2015年の記事です。
ただいまサイトの整理中で、漏れてる記事を再アップしてます(;^_^A
よろしかったらお読みください(^o^)】


![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)