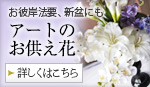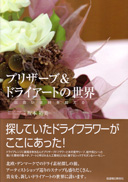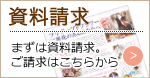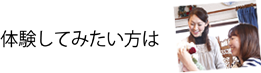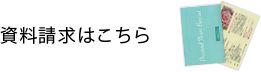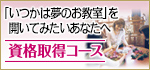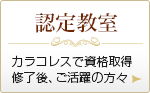体系的に整理されているものや
親切に説明してくれるものをもう信じない・・・とは
思うのだけれど。
表に出ていない「行間」を読むには
それなりの修行と力が必要のよう。
行間を自力で読めるようにならない限り
「木を見て森を見ず」の状態は続くのよね。
あ~頭いたい・・・。
子供の頃、
仲間の中に、年の割りに「大人びた言い回しをする子」がいると
借りてきた表現みたいに違和感を感じた。
親になり、
自分の子供が年の割りに「大人びた言い回しをする」のを聞いて、
成長したなあ・・・などと一瞬思ったのだが(笑える)、
その大人びた言い回しは本人のもの?
それとも借りてきたもの?
彼(小5の長男)の周りには、
マンガやゲームや本やテレビ、インターネット・・・
日々沢山の情報が押し寄せていて、
そんなごちゃごちゃな中で彼は作られてく。
当然オリジナルの表現も多彩になっていくはず。
こういう世代が世に出てくると面白いなあと思うと同時に
感じた事を自分の言葉で表現するのは逆に難しくなっていくのかも・・・。
誰もが聞き飽きた「言葉」が増えてきて。
斉藤美菜子の『文章読本さん江』で
明治の綴り方教育の形式主義を指摘しているのに、
まだ小さな子供達が遠足の作文で
「腰に水筒携えて」のような表現を入れるのが形式的に
ポピュラーだったという笑える話を読んだ。
(読み終わった本は処分しているので正確には確認できないけど)
選択肢が無くて、皆同じ表現をするから笑えたわけで、
私が子供のとき「大人びた言い回しをする子」たちもこんな感じ。
真似をする選択肢が無ければないで、
あればあったで、
どちらにしてもその中から「自分だけのもの」を探して
右往左往する事になるのね、きっと・・・。
その「右往左往かげん」が「自分だけの表現」ってことになるのかな?
「迷ってる自分」が独自と・・・。
全くの独自性なんてありえないものね。
素敵な感性をもった人の文章を読み始めると
最後まで読まないうちに、
自分の中で触発が起こってしまって困る。
ほんの数行を最後まで読まないうちに
私の中で何かが動き出してしまって、
それはもう「形」を作り出したくなってしまう。
で、一旦思ったことを書き留めたり、反芻したりして
もう一度その人の書いた続きの文章を読むと、
先ほどの感覚に戻れないときが多い。
まったくその瞬間にしかできないことって
あると思う。
スタッフからのメールに、
「了解」とだけ書いて返したところを長女が見ていて、
「ママ何っ! そのそっけなさ、信じられない!!」と叱責される。
「べつにいいじゃない、事務連絡だもん」と私。
「メール貰えるだけでもありがたく思わなきゃ。
それでなくてもママは友達少ないんだから!」と応酬される。
なるほど、彼女は「花の女子高生」ですからね・・・。
しかしこちらは仕事ですからね、
お友達のコミュニケーションとは違うのだ~!
「何処へもいけるし何でも出来る」って
幻想じゃないかと思うことがある。
車で道を運転していて
ごく走りなれた生活道路が
アスファルトの隙間から草が生えていて、
倒れた電柱や石の塊でふさがれている・・・なんて情景に
ふと画面展開するから。
「ここも少し前まで通れたのにねえ」なんて言ってる。
別にそんな映画観たわけではなくて、
人口減ってきたなあ、とか
税金でこんな田舎の隅っこの道まで直せるかなあ・・・なんて
思っているからか。
閉鎖したガソリンスタンドで一ヶ月もしないうちに
アスファルトを突き破り雑草が頭を出してきたのを
見たからかもしれない・・・。
「今できることをしっかりやっておこう」と
私の中で妙なところにつながってしまった。
「弦楽器をはじくのと弓で弾くのとどちらが好き?」
以前お筝の先生がそんなことをおっしゃっていた。
「私ははじく音が好き」と。私もそう。
もちろんお筝は爪ではじく撥弦楽器のほう。
三弦は撥ではじくまさしく撥弦楽器。
私は生田流だったから爪が四角で、
その角を使って、13本の弦を弾く。
准師範を取っていよいよ次はお三弦のお稽古・・・というころ
仕事が忙しくなって続けていられなくなった。
私が通っていた社中は週一の個人レッスンと
週にもう一日頻繁にある演奏会に向けての合奏練習という、
かなりハードなお教室だったのだ。
そこで10年近く修行(?)した。
今床の間にはソプラノ箏を入れて4面のお箏と
お三弦のケースが立てたまま。
きっと三弦は皮が破れているに違いないので、
恐ろしくてケースを開けられない。
けれど、私の夢は路地裏からもれ聞こえるお三弦と地歌・・・
なので、ある程度の年齢になったら
自分のペースでお稽古を続けなきゃ・・・。
でも今はとても無理。
そんなこと思っていたら、今日不思議な弦楽器の音を聞いた。
どこかの国の伝統音楽で(いい加減だ)、弦楽器なのだ。
しかもはじくほうの音・・・私、この音色好き~
音楽に関して全くの無知で、使われてる楽器さえもわからない。
悲しい。
弦を緩く張ってるのかな?
余韻がすごくきれいな音だった。
自分のその反応で、
人の嗜好ってそうそう変わるものではないのねって思いました。
実家の母から電話
「NHKで『とめはね』の再放送してるから見るように」
子供達が小さい頃からずっとお習字をしていて
長女は高校での部活もまさに「書道部」なのだ。
彼女のノートは芸術的に美しい。
一朝一夕にできないことで身につけたことって
意外と大きな参入障壁よねって思う。
(この場合は何の参入???)
イヤだったけど無理やり習わされていた事や、
大好きで小さなときから続けてきた事・・・
こういった雑多な経験が大事なときが来るのね。
私の場合は「幕の内弁当」的とりとめのない興味の詰め合わせだったが、
それぞれ夢中になった時期がある。
「表現する」のが仕事になった今、
その中の何一つ無駄にはなっていないと感じるもの。
あ~経験が大事! 寿命が足りないわっ!!
旧暦では立春が一年の始まりなのよね、
それより前の太古の暦では1月15日が「小正月」だし・・・。
だからグレゴリオ暦でしたっけ?太陽暦?西暦?新暦?・・・
とにかくそれらの新年を迎えたからって、
急に気分一新って感じにならないのは無理ないかも。
なんて反抗的。
まだ松の内なのに・・・。
もう新年のご挨拶もしちゃったのに。
(それはそれです、もちろん)
どちらかというと、今の私は整理したい気分。
つまり、まだ年末・・・。
それもこれもこれから来る新年めがけて動いていると考えれば、納得!
私は原始的な人間なので(友人にそう言われる)、
きっと身体がそう感じるのだわ!
勝手な解釈をつけて、
新年早々の緊張感の無さをいいわけするんだ~。
昨年の秋ごろから周りの時間の流れがとても速くなったみたい。
さすがの鈍感な私でも感じるくらいに・・・。
こんなこと、今まであった?
・・・無かった気がする。
私たちが扱っている作品たちは「時間に流されない」独自の存在だけれども、
実務に限ってはそうも言っていられないのが悲しいところ。
これからもずっとそのギャップを埋めていくことになると思う。
子供達が小さい頃いっしょに観た、
ミヒャエル・エンデの「モモ」の『時間』。
子育てに追われる中で感じた「そうよね、時間って・・・」と
改めて感慨にふけっていたのとも違う。
今になれば自分の持ち物だと断言できるのは「この先の時間」だけで、
それだって絶対ではないのでわからないのだ。
そう思うようになったからなおさら、
周りの時間の流れが気になるのかも・・・。
長男が7日から始まる小学校の持ち物の用意をしていて、
学習の評価(だいぶ古い言い方で言ったら通知表)に
「コメントを書いて」と持ってきた。
そう言えば「つうちひょう」って、
何だか特別な響きだったな~。
学期末の最後のHRの時間に
先生からひとり一人重々しく手渡されるんだったっけ・・・。
いつも成績の芳しくない私などは、
たいした期待も無かったので気が楽でしたけど(なぜ楽!?)
悲喜こもごもの思い出があるのでしょうね、皆さん。
それにしても「通知表」って、
今思えばただの「通知する表」だったのね。
音読みになったとたん特別な響きをもって情景も浮かぶって、
何だかすごいなと思って・・・。

![体験レッスンのお申込・お問合せはこちら 0120-112-897 [受付時間]9:00〜20:00(土・日・祝日も営業)](/images/common/header-tel3.gif)